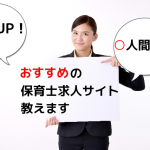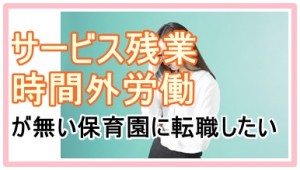保育園・幼稚園の大きな行事の一つに、「お泊まり保育」があります。
子どもにとって、子どもが親元を離れて過ごす経験は貴重なものです。
しかし、いざ当日となると、子どもも保護者も不安でドキドキしますよね。
お泊まり保育当日の、職員の準備はかなり大変です。
とくに、行事の大目玉である夜のレクリエーションは、念入りに計画を立てて行わなければなりません。
この記事では、お泊り保育を控えている現役保育士・幼稚園教諭向けに、お泊り保育のねらいや、おすすめの夜のレクリエーションについて紹介します。
スポンサーリンク
保育園・幼稚園で行われるお泊まり保育のねらい・目的は?
お泊まり保育のねらいは大きく分けて3つあります。
〇親と離れて自立心を促す
〇友達や先生とのきずなを深める
〇集団生活の中で規則正しい生活を身につける
子どもたちが、この年齢で親元を離れて生活をする機会は少ないです。
親がいると、ついつい甘えて食事の準備やおかたづけなどの手伝いをしなかったり、夜更かしをしてしまう、子どもも多いと思います。
ですが、お泊まり保育は『友達と先生との集団生活』です。
子どもたちは、お泊まり保育を通して、自分たちで身の回りのことをするという自立心、そして規則正しい生活を身につけます。
そして、食事作りやレクリエーションなどの楽しさを共有して、友達や先生とのきずなを深めることができるのです。
以上のように、お泊り保育は子どもが成長する上で大切なことがたくさん詰まった貴重な行事となっています。
お泊まり保育の内容と流れ
- 登園
- 先生のお話
- レクリエーション
- 夕食作り
- レクリエーション
- 入浴
- 着替え
- 就寝
- 起床
- 朝の体操
- 朝ごはん
- 先生のお話
- お迎え
お泊り保育は、子どもたちが日中活動している保育園や幼稚園で一晩過ごします。
中には、宿泊施設を借りて行うところもあるようですが、子どもの不安を最小限に抑えるために、慣れ親しんでいる園を宿泊先に選ぶ保育園・幼稚園が多いです。
当日は、15:00ごろに登園し、子どもたちは保護者と別れます。
その後は、ウォーミングアップとしてのレクリエーションをしてから夕食作りをします。
メニューは「カレーライス」が人気ですね。
夕食後は、目玉の「夜のレクリエーション」があります。
昼間ではなく、夜にみんなでゲームをするという、いつもと違うシチュエーションに大興奮する子どもたち。
盛り上がる半面、ケガや事故に気を付けなければなりません。
たくさん楽しんで汗をかいた後は「入浴」です。
これは、登園前に家で済ませるように保護者にお願いをしたり、園のシャワールームを貸したり、スーパー銭湯に行ったり、園によって入浴場所が変わります。
その後はパジャマに着替え、ホールや保育室に布団を敷いて就寝。
子どもたちが寝たら職員でミーティングを行い、翌日に備えます。
翌朝、朝の体操をしてから朝食、そして全員集合して、保護者のお迎えで解散となります。
【お泊まり保育の実態】先生たちは徹夜?
お泊り保育の夜、職員はほぼ徹夜です。
なぜなら、子どもが夜中にトイレに行くのに付き添ったり、親がいない不安で泣き出してしまう子に声を掛けたり、寝相が激しい子どもの布団の位置を直したり、様々な対応をしなければならないからです。
しかし、職員全員が徹夜するわけではありません。
0~2時、2~4時のように数時間おきに交代制で見回ります。
よって、仮眠することはできますが、子どもたちが近くにいて、他の職員が起きている状況では、とても寝つけません。
わたしも気が休まらず、結局一睡もできず、朝を迎えた経験があります。
子どもたちの楽しそうな顔を見られるのは嬉しいですが、園の行事で1、2位を争うほど過酷な行事でした。
お泊まり保育についての保護者からの口コミはどう?
お泊まり保育は、子どもだけでなく保護者にとっても一大イベントです。
実際に、保護者はお泊まり保育についてどう感じているのでしょうか?ここでは、保護者によるお泊り保育につての口コミを紹介していきます。
本人は楽しみにしてますが、甘えん坊なので、親の私の方が心配です。(YAHOO!知恵袋)
子どもは案外、お泊り保育を楽しみにしているようですが、やはり、親元を離れる我が子の心配をする保護者の声が多いですね。
翌朝、お迎えの時間にフライング気味で行きましたが本人は「楽しかったぁ♪もっと泊まりたい♪」とキラッキラの自信をつけた笑顔で私のもとへ帰ってきました。(YAHOO!知恵袋)
いつもと違う環境で、友達や先生と過ごす経験は子どもにとって、かけがえのない楽しい思い出です。
我が家も年少の頃の1泊だけで、ずいぶん自信がついたのかたくましい顔つきで帰ってきたの思い出しました。(Twitter)
親元を離れて過ごす経験は、子どもの自信になります。
「一人でもできる!」と自立心を養うことはお泊り保育の大切な役割です。
お泊り保育での経験は、「苦手な野菜を食べられた!」という自信になったようです。(Twitter)
お泊り保育の夕食作りで、子どもたちが野菜を切る場面があります。
自分たちで作った料理は、たとえ野菜が入っていてもおいしいものです。
心配する一方で、ひとまわり成長して帰ってきた我が子を誇らしく思う保護者の声が多くありました。
親は我が子を信じること、子どもは自活力を身につけること、それぞれが大切なことを学ぶ貴重な行事ですね。
大盛り上がりの「おすすめの夜のレクリエーション」4つ
きもだめし
お泊り保育は、夏に行われることが多いです。
そのため、夏の風物詩であるきもだめしが鉄板のレクリエーションといえます。
保育室をお化け屋敷風に装飾すれば、雰囲気作りは完璧です。
装飾をしなくても、電気を消した園内を回ったり、職員がお化け役として登場したり、工夫を凝らせば十分盛り上がります。
怖がりの子もいるので、職員が手をつないだり、適度に明かりをつけたり、しっかり配慮すれば楽しむことができますよ。
先生あてクイズ
職員が変装をし、それを子どもたちがあてるというクイズ。
司会の職員が、変装した職員にインタビューをしていき、この回答をもとに子どもたちがあてていきます。
仮面をつけたり、着ぐるみを着たり、子どもたちが目で見て楽しめる演出が大切です。
チームに分かれて得点を競ったり、参加証として手作りのプレゼントをあげても良いですね。
宝探し
宝物を用意して、隠す側と探す側に分かれます。
宝物は手作りのコインや、既製品のプラスチックのダイヤを使うと、雰囲気作りができます。
ゲーム開始前に、部屋の高いところや危険な箇所は避けるよう呼びかけをしましょう。
お手本として、職員が隠してみるのもいいですね。
隠している最中は、探す側の子どもが目をつぶり、数を数えます。
隠し場所は要所要所、職員がアドバイスをして、パターン化しないようにしましょう。
もうじゅうがりにいこうよ
「もうじゅうがりにいこうよ♪~」というハンター(先生)の掛け声の後に子どもたちが同じように真似をします。
そして、最後に「○○(動物の名前)!」とハンターが言った後、その動物の名前の文字数に合わせた人数の友達と手をつなぎ、人数が揃ったらその場に座ります。
例えば、「キリン」なら3人、「ライオン」なら4人、「マウンテンゴリラ」なら8人が集まり、手をつなぎます。
人数が揃わなかったチーム、集まるのが遅かったチームはハンターに捕まります。
捕まったチームがハンター役になっても良いですね。
お泊まり保育を無事に終えるには
お泊り保育では、子どもと一緒にいる時間が長いため、様々な配慮が必要になります。
食事作りでは子どもがケガをしないようにきちんとそばで見守ったり、夜も異変がないかどうか徹夜で見回ったり、とにかく職員は息をつく暇もないほど大変な行事です。
しかし、お泊り保育が終われば、一回り成長した子どもの姿を見ることができます。
子どもを見守ると同時に、レクリエーションなどで工夫を凝らし、楽しいお泊り保育を作っていきましょう。