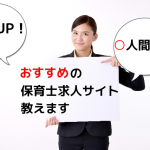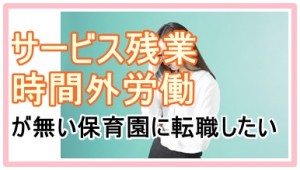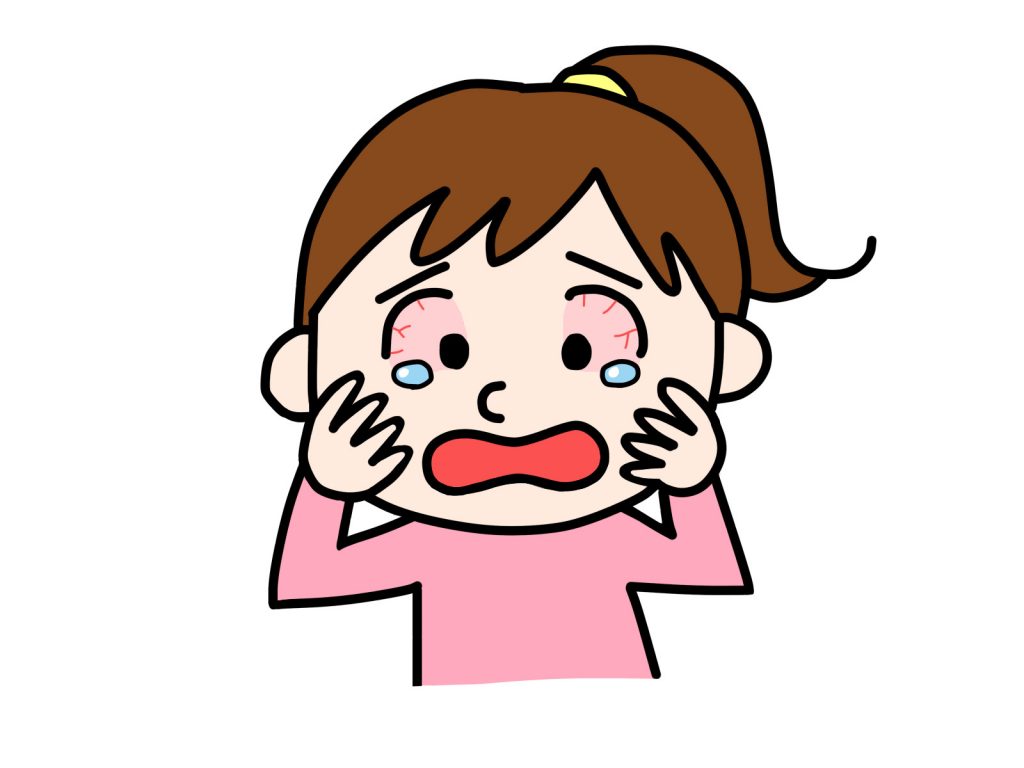
スポンサーリンク
夏に流行るプール熱(咽頭結膜熱)とは?
プール熱は(咽頭結膜熱)は、主にアデノウイルス3型(稀に4型)が原因で発症し、急な高熱やのどの痛み、結膜炎などの症状を引き起こすことで知られる夏風邪の一種です。
正式な疾患名は「咽頭結膜熱」ですが、プールの水を介して感染する事が多く、「プール熱」と呼ばれ広く知られています。
しかし、実際はプールに入らなくてもくしゃみや咳、タオルの共用などで感染することもあるので十分注意が必要です。
流行しやすい時期は、一般的に6~8月頃で、6月頭から少しずつ感染者が増加し、7~8月頃に感染者数のピークを迎えます。
プール熱に感染する人の70%が5歳以下の乳幼児とされていますが、大人が感染するケースもあるので油断しないようにしっかり予防と対策を心がけましょう。
プール熱(咽頭結膜熱)の主な症状の特徴
※5つのサインを見逃さないで!
(1)38℃以上の急な発熱
(2)のどの腫れと痛み
(3)目が真っ赤になり痛む
(4)目やにがでる
(5)頭痛や吐き気がある(腹痛や下痢を起こす場合もある)
プール熱に感染するとどんな症状がでるの?
プール熱(咽頭結膜熱)に感染すると、38℃~40℃の急な発熱と頭痛、のどの腫れや痛み、全身の倦怠感などの風邪に似た症状を引き起こします。
また、結膜炎の症状でもある目の充血(目が真っ赤になる)や目やになどもこの病気の特徴で、場合によっては痛みを伴ったり、涙が出たり、まぶしく感じる場合もあります。
大抵は、いきなり両目に症状が現れるのではなく、片方ずつ始まり徐々に広がっていくのが一般的です。
また、プール熱にかかると、のどの痛みで食欲がなくなるケースも多いので、なるべく食べやすいものを選び、水分補給を欠かさないように心がけましょう。
潜伏期間と感染期間
潜伏期間:5~7日
感染期間:10~14日間(排泄物からの感染期間は3~4週間)
プール熱の症状が確認されるまでの期間は5~7日で、特有の症状が出始めたら感染したとみなされます。
このウイルスは初期に感染力が強く、3~5日経つにつれて徐々に弱まっていきます。
しかし、感染力が弱まったとしても感染しないわけではないので、2週間は様子を見て注意するようにしましょう。
また、1ヵ月間は排泄物からのウイルス排出が続くので、トイレの後の手洗いは忘れずにしっかり行いましょう。
プール熱(咽頭結膜熱)の感染ルートを知ろう!
主な感染経路は2つあります!
飛沫感染:咳やくしゃみによって唾液が飛散し感染する
接触感染:ウイルスの付着した手や物で粘膜に触れることで感染する
この感染症は、プールの水を介して目の粘膜にウイルスが侵入したり、ドアノブ、手すりなどからも感染することがあります。
特に、プールの時期はタオルを使用する機会が多く、二次感染を引き起こしやすいといえます。
また、一般的な風邪と同じで咳やくしゃみなどでうつる可能性もあるので、マスクの着用や手洗い・うがいがとても大切です。
プール熱(咽頭結膜熱)の予防方法を確認しよう!
- むやみに目をこすらない
- 手洗い・うがいの徹底
- タオルやハンカチの共用はしない
- プールに入る際は体を清潔にする
- 十分な睡眠とバランスの良い食事
感染すると長引くプール熱の予防法は、一般的な風邪と同様、手洗い・うがいの習慣を身につけることや、友達とタオルを共用しないようにすることです。
また、目の粘膜ににウイルスが入り込み感染するケースもあるので、普段から目をこすらないように気を付け、どうしても…という時は手を清潔にした状態でこするように注意してください。
この病気は、免疫力が落ちている時に感染しやすいので、普段から十分な睡眠と栄養たっぷりの食事を摂り、健康な体作りを心がけましょう。
保育士がチェックすべき感染症状
※園児に以下の症状が見られたらプール熱に感染しているかも?
- 目のかゆみを訴えてくる
- 目が充血している
- 非常に高い熱が出てぐったりしている(38℃~40度前後)
- 目やにが出ている
- 頭痛や吐き気を訴えてくる
このような症状が見受けられる場合はすぐに適切な対処が必要です。
保育園でできるプール熱の予防と対処法とは?
<保育園の予防法>
〇 毎日の手洗い・うがいを習慣付ける
〇 友達同士でタオルやハンカチの貸し借りをしないように呼びかける
〇 プールに入る時は体をきれいに洗う
<保育園での対処法>
〇 感染した疑いのある園児は、別室で保育を行う
〇 目をこすらないよう呼びかける
〇 感染者が出たことを伝え、予防を呼びかける
〇 プールの一時的な閉鎖(感染者が急増した場合)
プール熱に感染したら登園停止になるってほんと?
※正しい登園基準の確認をしよう!
厚生労働省のガイドラインには以下のように記載されています。
登園のめやすは、主な症状(39℃前後の発熱、咽頭発赤、咽頭痛、結膜炎)が消え2日以上経過してから
「保育所における感染症対策ガイドライン」(厚生労働省より)
プール熱(咽頭結膜熱)は、学校保健安全法の指定感染症なので、熱やのどの痛み、結膜炎などの症状が消えた後から2日経過するまで登園できません。
回復後、園児が登園するためには、医療機関を受診して医師に「登園許可書」の提出を行う必要があります。
この感染症は、ほかの夏風邪(ヘルパンギーナ・手足口病)と違い、出席停止期間が公的機関により定められているので、感染拡大を起こさない為にもしっかり予防しておきましょう。
Q「プールはいつからOKすればいいの?」
登園するようになったらプールにも入っていいと思われがちですが、最低2週間は控えておいた方が無難です。
なぜなら、プール熱を引き起こすアデノウイルスは非常に感染力が強く、手洗いなどの予防をしていたとしても、水を介して感染する恐れがあるからです。
他の園児への感染リスクを減らすためにも、最低2週間はプール遊びを行わないようにしましょう。
注意!油断は禁物!大人が感染する可能性も…
※大人の感染症状
〇 38℃以上の高熱
〇 のどの腫れや痛み
〇 目の充血や目やに
子どもの感染症状とほとんど同じですが、感染後の症状が比較的軽いのが特徴で、1週間ほどで完治します。
しかし、稀にプール熱から胃腸炎や流行性角結膜炎など数種類の合併症を引き起こすこともあるので十分注意しましょう。
また、保育士の場合、子ども達とプールに入る機会や同じ部屋で過ごす時間が長いので、日頃から予防を心がけ感染しないように気を付けましょう。
保育園でかかりやすい?プール熱(咽頭結膜熱)の感染事例
<事例1>
7月中旬、保育園でプール熱が流行りはじめ、5歳児クラスで数名が感染。
最初に感染した子は1週間前から欠席しているのですが、感染者が増えていく一方なので、保護者へ注意を呼びかける手紙や張り紙をする。
担任を含め、職員間での情報交換はこまめに行っていたつもりだったが、プールを継続していたため感染者が増えたのでは?と保護者よりクレームが入る。
すぐに職員会議を開き、プールの一時閉鎖の措置や手洗い・うがいを今以上に徹底するなどの対策を立てる。
後日保護者へ向け、プール熱を予防するための対策方法を説明し納得してもらうことができた。
<事例2>
6月、1歳児クラスのSちゃんがぐったりしているので熱を測ると38.5℃ある事がわかる。
すぐに別室へ移し保護者へ迎えの依頼を行うが、その間にも熱は上がり39℃台になっていた。
朝からの様子を保護者に伝え、すぐに医療機関へ受診するようにお願いする。
その後連絡が入り、プール熱だったことが分かった。
後々聞いた話によると、「お姉ちゃんが通うスイミングスクールで、プール熱が流行っていたのでもらったのかも?」とのこと。
幸い他の園児に感染することはなく、Sちゃんも1週間後に元気に登園することができた。
<事例3>
朝、出勤前に鏡を見ると目の中が少し赤いような気がしましたが、「目が充血しているのかな?」くらいにしか思っていませんでした。
特に、今年は年長児を担任していることもあり、例年よりプールの入る機会が多く、「また眼科に行けばいいや!」と軽く考えていました。
しかし、保育を行っている最中に発熱したため、今日は帰るようにとの指示が出る。
念のために病院へ行き検査してもらうと、プール熱に感染していることが分かった。
すぐに保育園へ連絡を入れ状況を伝え、1週間お休みをもらう事となった。
☑感染事例から対処法や予防法を学ぼう!
事例からわかるように、プール熱はとても感染力の強いウイルスなので、予防を怠ったり「ただの風邪でしょ?」なんて思っていてはすぐに感染してしまします。
このウイルスは、一度感染すると1週間近く登園や勤務ができなくなるので、今一度しっかりとした対策と予防法を実践することをおすすめします。
また、最近のスイミングスクールは温水プールが主流なので、プール熱が年中流行りやすい環境にあるので、習い事をしている子や兄弟がクラスにいるなら十分注意が必要です。
プール熱は、発症期間はもちろんのこと、諸症状が治まってからも感染する可能性があるので、被害を拡大させないためにも十分気を付けましょうね。
夏バテしやすい季節ですが、保育士もしっかり体力をつけ、子ども達と元気に夏を乗り切りましょう!