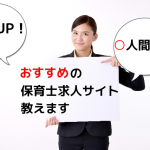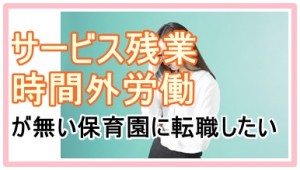スポンサーリンク
溶連菌感染症とはどんな病気?
溶連菌感染症とは、のどの痛みや炎症、急な発熱などの風邪と間違えやすい症状から始まり、徐々に全身にかゆみや発疹、イチゴ舌などの特徴的な症状が現れる感染症です。
感染者の中には、中耳炎やとびひ、合併症にかかる人もいるので、充分注意が必要です。
気になる流行時期は冬と春夏の年2回で、A群溶連血性レンサ球菌と呼ばれる細菌が原因で発症し、保育園などの集団生活の場では、感染が広がりやすいので、徹底した予防と対策が重要です
溶連菌感染症に最もかかりやすい年齢は、5歳~12歳とされていますが、大人や乳児に発症したというケースも報告されているので油断は大敵です。
知っておきたい!溶連菌感染症の主な症状
※こんな症状があれば感染の可能性も!
- のどの痛みが2日以上続く
- 咽頭発赤(のどちんこに赤いブツブツができる)
- 急に高熱が出る(38℃~39℃前後)
- 舌が真っ赤に腫れ、ブツブツができる(イチゴ舌)
- かゆみを伴う発疹が全身に広がる
溶連菌に感染すると、2~4日の潜伏期間を経て、急な発熱やのどの痛み、嘔吐、頭痛などの風邪に似た症状があらわれます。
症状が風邪に似ているため感染したことに気付かず、1~2日たって全身の発疹やかゆみ、イチゴ舌などの症状で気づくこともありますが、「いつもと違うな!」と感じたら、すぐに医療機関で検査を受けましょう。
例外として、乳幼児に感染した場合、熱が出ないまま重症化する恐れもあるため、十分注意が必要です。
症状自体は、病院から処方される抗生物質を飲むことで落ち着きますが、合併症にかかるリスクがあるため、薬は途中で止めずに最後まで飲み切りましょう。
気になる溶連菌の感染経路と予防法
※感染には2つの経路があった!
(1)飛沫感染:感染者の咳、唾液の飛散、くしゃみ
(2)経口感染:細菌が付着した飲食物の摂取
溶連菌の感染力がピークを迎えるのは発症した頃で、次第に感染力は弱まっていきますが、保育園などの集団生活の場や、同じ家で暮らす兄弟間で二次感染を起こす確率が高いので、日頃から予防を心がけましょう。
※溶連菌感染症の予防法
この感染症は事前に予防接種を受けて予防することができないので、手洗い、うがい、マスクの着用など一般的に知られている風邪予防が効果的だとされています。
特に、保育園では感染者が使用したコップや水筒、お皿、おもちゃなどを共有することでうつる可能性があるため、よく除菌しておくか一緒に使わないよう呼びかけましょう。
溶連菌感染症は、子どもだけに感染するわけではなく、免疫力の落ちた大人に感染するケースもあるため、体調管理にしっかり行い予防に心がけましょう。
症状が治まっても合併症に注意!
子どもが溶連菌感染症にかかったら、抗生物質(10日~2週間分)処方されるのが一般的ですが、最後まで飲みきらなないと細菌が死滅せずに繁殖し、合併症のリスクが高くなります。
ここでは、主要な合併症を2つ紹介します!
・リウマチ熱
リウマチ熱は、溶連菌のアレルギー反応によって起こる炎症の一つで、感染してから2~4週間後に発症し、高熱、心膜炎、関節痛などの症状が現れます。
また、後遺症として心臓弁膜症を引き起こすこともあるので、早期治療と適切な処置が求められます。
・急性糸球体腎炎
急性糸球体腎炎は、溶連菌の感染後に引き起こされる病気で、血尿、尿たんぱく、むくみ、高血圧などの症状を引き起こします。
また、重症化してしまうと、急性心不全や高血圧性脳症を引き起こす場合もあるので十分注意が必要です。
保育園でできる溶連菌感染症の予防と対策
<保育園での予防>
- 飛沫感染しやすいので、マスクの着用を促す
- 接触感染にはうがい・手洗い・園全体の掃除を徹底する
- アトピー性皮膚炎の症状がある園児は、溶連菌感染症を発症することで重症化しやすいため、流行時期には前もって保護者に知らせるようにする。
<保育園での感染対策>
- 園児がのどの痛みを訴えたり、突発的な熱を出した時は、「溶連菌感染症」を疑い、保護者へ連絡を入れ速やかな受診を促す。
- 発疹が確認された場合は別室で保育を行う
- 感染拡大を防ぐために、保育園での感染状況を各家庭へ発信し、予防につなげる。
保育士は、日頃から園児の健康状態を把握し、少しでも「おかしいな?」と感じたらすぐに園の責任者へ報告し、保護者への迎えをお願いしましょう。
溶連菌感染症は重症化しやすい病気なので、保育士が症状や特徴を事前に頭の中に入れおくことで迅速に対応すことができ、早期治療へと繋がっていきます。
また、保護者から検査結果の連絡が入った際、園全体で情報共有ができる体制を整えておきましょう。
発症した子どもの登園停止期間について
溶連菌感染症を発症した際の登園めやすは、医療機関で処方された抗生物質を服用しれから24~48時間以上経過していること。
「平成26年 保育所における感染症ガイドライン」(厚生労働省)より
上記の内容を踏まえ、登園停止期間の基準をまとめてみたので参考にしてください!
〇 一般的には受診日を含めて2~5日の登園停止となる
〇 抗生物質を飲んで24時間以内は登園許可が出ない
〇 日数が経過しても症状が出ている場合は登園できない
〇 各保育園によって基準が違うので予め確認が必要
保育園での溶連菌感染症の感染事例
(事例1)
近隣の小学校で溶連菌感染症が流行っていたが、保育園に感染している子がいなかったので気にも留めていませんでした。
しかし、数日たって3歳児の女の子が「給食が食べられない!」と不調を訴え徐々に熱も上がってきたので、風邪かもしれないと思いお迎えをお願いする。
その次の日も熱が下がらず、保護者が女の子を連れて医療機関を受診すると、溶連菌感染症と診断されたと園に連絡が入る。
良く考えてみれば、女の子には小学生の兄がいるので、兄弟感染した疑いがある事に気付く。
(事例2)
保育園でプールが始まり数日、風邪のような症状が出ているという連絡を受け迎えに行き、家で様子を見るが、急に全身に発疹が出始めたため小児科を受診する。
最初は塩素によるアトピー性皮膚炎の悪化と思われたが、のどの痛みや熱の事を話すと溶連菌の検査を進められ、結果感染していることがわかる。
園に連絡を入れると、他にも感染している園児が数名いるとのこと。
抗生物質を服用して症状が治まったので、4日後に登園することができた。
※事例で共通することは、保育士が感染に気付かず受診が遅れてしまったという点です。
もちろん保育士は医療従事者ではないので診断まではできませんが、ある程度の知識を身に付けておくことで予防することができたり、病気のリスクを減らすことができます。
また、近隣での感染報告があった場合は軽視せずに、保育園でできる予防や対策を練るなど、常に危機感を持って行動できる保育士でありたいですね。