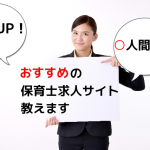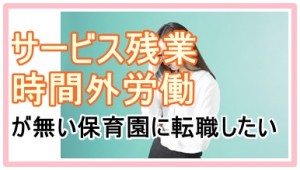スポンサーリンク
ノロウイルス感染症とは?
ノロウイルス感染症とは、年齢に関係なく発症する「感染性胃腸炎の一種」です。
年間通して発生しますが、特に11月~3月時期に感染者が多く、嘔吐や下痢という辛い症状を引き起こすことで有名です。
ノロウイルスは、汚染されたカキなどの二枚貝を食べることで感染・発症する確率が高いと言われていますが、学校や保育園などの集団施設では、感染者の嘔吐物や排泄物からの二次感染が多く、発症原因が特定できない事例も沢山あります。
また、感染者が料理を作る際、手洗いが不十分なまま調理することで食品が汚染され、その食品を食べることで感染する恐れがあるので、日頃から徹底した衛生管理が重要です。
ノロウイルスで特に注意すべき5つの特徴
- 少量のウイルスでも感染する(10~100個)
- 特効薬やワクチンが無い
- 次亜塩素ナトリウムを使用するか、85℃~90℃で90秒以上の加熱でしかウイルスを不活化できない
- 一度ノロウイルスに感染していても、繰り返し感染する可能性がある
- 人の腸管でしか増殖できない
ノロウイルス感染した場合の症状・潜伏期間は?
症状:水のような下痢・吐き気・嘔吐・腹痛・発熱・頭痛
潜伏期間:平均24~48時間(1~2日)
※嘔吐や下痢に関しては1日に数回繰り返します。
ノロウイルスに感染すると嘔吐や下痢が続き、乳幼児は脱水症に陥りやすく、重症化しやすいので、特に注意が必要です。
現在、ノロウイルスに効く特効薬は開発されていませんが、一般的には3日程度で症状は落ち着き、次第に回復していきます。
中には軽症で回復したり、症状が出ないケースもありますが、10日~30日間は感染者の便からウイルスが排出されることもあるので、二次感染には十分注意しましょう。
ウイルスの感染経路
接触感染:ウイルスに触れることで感染する
経口感染:ウイルスが付着した飲食物を摂取することで感染する
飛沫感染:飛散ったウイルスを吸い込むことによって感染する
<ノロウイルス感染の流れを知っておこう!>
- 感染者がノロウイルスを排出する
- 汚染水が川から海へ流れる
- 二枚貝の内臓にウイルスが蓄積される
- 加熱不十分の二枚貝を食べる
- 感染者が料理を作る
- ノロウイルスが付着した料理を食べる
※感染者が使用した「トイレのドアノブ」や「ペーパーホルダー」に触れるだけで感染するケースも考えられます。
保育園でのノロウイルス発生時の対応と予防のポイント
・発生時に保育士が取るべき行動
園児に感染の疑いがある場合は、周辺にいる子どもを別室に移動させ、部屋の窓を開けて換気を行い、速やかに嘔吐・下痢の処理を行います。
また、感染の疑いがある園児は別室で保育し、引き続き嘔吐する可能性を考慮してバケツや消毒液、タオルを用意しておきましょう。
嘔吐や下痢がひどい場合は、「脱水症状」が出やすいので、吐き気を誘発しない程度の水分補給(経口補水液)を行いつつ、急に吐き気を催した場合は、慌てずに静かに座らせるか横向きに寝かせ、嘔吐物を詰まらせないようにしっかり視診しておきましょう。
・関係機関や保護者への報告と連絡
ノロウイルスに感染した疑いがある場合は、すぐに保護者へ連絡を取り、お迎えの依頼を行いましょう。
来園された際、園児の状態や経過を詳しく話し、医療機関への速やかな受診を促すと共に検査結果が出た際は報告をお願いしておきましょう。
各関係機関には園の責任者が連絡を取り、発生日時や感染人数などの詳しい状況を随時報告します。
・感染拡大を未然に防ぐ5つのポイント
- 園全体の手洗いを徹底する
- 嘔吐物・排泄物の適切な処理を心がける
- 保育室・トイレ・おもちゃの消毒をこまめに行う
- 調理室での食品管理と調理器具の加熱処理と消毒を徹底する
- 子どもの健康状態を日々観察して変化に気付く
・二次感染を防ぐ手洗い方法!
<正しい手洗いの手順>
(1)手についた付着物を流水で洗い落とし、薬用石けんを良く泡立てる
(2)しっかり洗っていても、指の間や手首などは汚れが残りやすいので、20秒~30秒かけて丁寧に洗う
(3)洗い残しが無いか確認し、流水で丁寧に洗い流す
(4)使い捨てのペーパータオルで水分を拭き取る
※しっかり時間をかけて洗い流すこと!
嘔吐物・排泄物の適切な処理方法
感染者の嘔吐物や排泄物には1gあたり約100万個~1億個ものノロウイルスが含まれいるので、適切な処理を行わないと二次感染を引き起こす可能性も十分考えられます。
また、ノロウイルスは乾燥に強く、塵や埃と一緒に舞い上がり飛沫感染を引き起こす危険性もあるため、すぐに処理するよう心がけましょう。
<必要な準備物>
- 使い捨てマスク
- 使い捨てビニール手袋
- 使い捨てエプロン
- 汚物を入れるビニール袋(二重が望ましい)
- ペーパータオルやぼろ布
- 薬用石けん
- 消毒液(次亜塩素ナトリウム)
<処理の手順>
(1)室内の窓を開けて換気を行う
(2)エプロンや手袋、マスクを着用してから処理を行う
(3)嘔吐物をペーパータオルやぼろ布を使い挟み込むようにふき取りすぐにビニール袋へ入れ袋の口を閉じる(消毒液をかけて閉じるのがベスト)
(4)嘔吐物をふき取った場所を消毒液をしみこませた別のペーパータオルやぼろ布で拭いておく
(5)処理に使用した物は全てビニール袋に入れて廃棄する
(6)廃棄できないものは消毒液に浸すか、85℃で1分以上の加熱を行いよく乾燥させる
(7)処理を行った人は、しっかりと手洗いを行い二次感染を予防する
<消毒液の作り方>
準備するもの
- 5%次亜塩素酸ナトリウム(家庭用塩素系漂白剤に含まれる)
- 空のペットボトル(500mlが望ましい)
- 水(適量)
作り方
(1)直接手に触れると危険なので、手袋とマスク、エプロンを着用し作業を行います。
(2)ペットボトルに水を入れ、次亜塩素酸ナトリウムを入れて(下記の表を参照)薄めます。
(3)使用場所によって濃度が違うので、誰が見てもわかるようにマジックなどで使用場所を記載しておきましょう。
注意!
消毒液を取り扱う際は、換気を十分に行い直接液に触れないように注意し、金属や色落ちが気になる衣類への使用は極力控えましょう。
また、消毒液は時間が経過すると共に効果が落ちるので、その都度作り直して使用することをおすすめします
| 使用場所 | 消毒液の濃度 | 使用する物 |
| 嘔吐物や排泄物が直接付着した箇所 | 0.1% | 次亜塩素酸ナトリウム10ml(ペットボトルキャップ2杯分)水500ml |
| 感染者が触れたと思われる箇所 (おもちゃ、ドアノブ等) | 0.02% | 次亜塩素酸ナトリウム10ml(ペットボトルキャップ2杯分) 水2.5L |
保育園内のウイルス撃退方法
・おもちゃ類の消毒方法
(1)消毒液(次亜塩素酸ナトリウム0.02%)に10分以上浸すか、85℃以上の熱湯に1分以上浸す。
(2)よく洗い流し、しっかり乾燥させて使用する。
※おもちゃの素材によって消毒方法を選んで行いましょう。
・施設全体の消毒方法
(1)換気を十分に行い、廊下、手すり、蛇口、ドアノブ、窓ガラス、椅子、つくえ等、手で直接触れる場所は消毒液(次亜塩素酸ナトリウム0.02%)を含ませた雑巾で拭きあげる。
(2)どこにウイルスが付着しているかわからないので、しっかりと消毒を行いましょう。(使用済み雑巾は廃棄が望ましい)
・布団や衣類の消毒方法
色落ち・洗濯可能な布団や衣類の場合
(1)洗い桶に消毒液(次亜塩素酸ナトリウム0.02%)を入れ、布団や衣類を10分間浸す。
(2)よく洗い流し、通常通りに洗濯機を回す。
(3)長時間日光に当てて干すか、乾燥機で十分乾かす。
洗濯できない布団や衣類
(1)スチームアイロンを使用し、85℃以上の蒸気を当ててウイルスを撃退する。
※直接布団や衣類に当てないように注意する!
保育園でのノロウイルス感染事例から学ぼう!
<事例1>
某保育園で、園児26名、職員11名の計37名の集団感染が報告された。
始まりは、嘔吐で休むという連絡が8件入り、不思議に思った職員が各クラスに健康状態を確認したところ、2日前に廊下で嘔吐した園児がいたことが分かった。
その後、感染はどんどん広がり、クラス閉鎖が行われるなど早急に対策がとられた。
<事例2>
某保育施設で0歳児が嘔吐した。
園児の機嫌もよく、噴射するような嘔吐ではなかったため、保育士は水拭きで嘔吐物を処理した。
しかし、保育室にいた他の園児にも嘔吐や下痢の症状があらわれノロウイルスに感染していたことが分かった。
どちらの事例も、最初の嘔吐で保育士が気付かず、見過ごしてしまった事による感染拡大でしたが、日頃から園児の健康状態を把握し、「もしかして何かの病気かも?」と疑ってかかる事も必要だと気付かされます。
ノロウイルス感染時の登園許可の目安は?
ノロウイルスは、学校保健安全法による明確な出席停止期間の定めがないため、嘔吐や下痢がなく日常生活が送れるほどに回復したと判断したら、医療機関への受診を行い、医師の許可を得てから登園となります。
また、園によっては「登園許可書」が必要な場合もあるので、予め確認しておくことをおすすめします。
保育士もノロウイルスを予防しよう!
- 十分加熱処理した食材(カキ、ハマグリ)を食べる
- 正しい手洗い方法を習慣化する
- 調理台や調理器具をこまめに消毒する
- ラクトフェリンを含むヨーグルトを食べる
保育園でノロウイルスが発生した場合、保育士も一緒に感染してしまうケースが多く、保育園が再開できない…なんて事態になりかねません。
どんなに病気の対処法を身に付けても、自分が健康でなければ子ども達をウイルスから守ることはできません。
日頃から上記のような予防を心がけ、ウイルスを寄せつけない健康な身体作りを行い、元気に保育ができるよう努力しましょう!