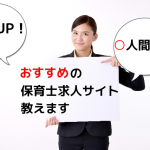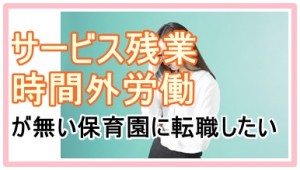スポンサーリンク
6歳児(年長さん)の発達と主な特徴
- 全身運動が巧みになる
- 協同遊びができる
- 友達との関係が親密になる
- 見通しを立てて行動できる
- 自然事象や社会事象、文字への関心が高まる
- 身近な大人に我儘を言ったり甘える時もある
- 年長児としての自信や誇りを持つ
- 自立心が高まり、就学への期待や意欲を持つ
6歳児の成長と特徴
活発な運動機能
6歳児ともなると身体的な機能は成熟し、より俊敏で活発な姿が見られるようになります。
例えば
- リレーや徒競走など全速力で走る運動
- 跳び箱や竹馬
- 縄跳び走りなどの用具を使った運動
まで巧みにこなし、大人を驚かせることもしばしばです。
また、年長児としての自覚や誇りを持つ時期でもあり、苦手な運動や出来事に遭遇しても、意欲的に取り組む姿を見せてくれるようになります。
手先の動きがより活発に!
手先の動きも滑らかになり、技巧性が格段に向上します。
- 話を聞いてその情景を絵で表現する
- 紐をリボン結びやこま結びにしてほどく
- 雑巾を固く絞れる
- ハサミやホチキスなどの道具を上手く使いこなせる
このように手先が器用になります。
このような製作活動や日常動作を通して、幅広い表現力や意欲性を高め、子どもは健やかに成長していきます。
協同遊びとごっこ遊び
大人との関係よりも友達同士の関係が親密になり、秘密や約束事を大切にしたり出来る限り守ろうとする6歳児。
この頃になると、集団の中でお互いが協力し合いながら遊びを発展させていく「協同遊び」が盛んになり、それぞれに役割を担って活動していく姿が見られると共に、ごっこ遊びの役割も複雑になり、手の込んだ設定と流れを作って遊ぶようになります。
時には脱線したり失敗することもありますが、友達同士で話し合いながら試行錯誤して楽しむことができるようになっていきます。
6歳児の社会性
集団の中の一人として行動し、友達から認められたり遊びの楽しさを共有することを求める6歳児。
仲間との関わりの中で、
- 経験や知識を活かし、新しい方法や手段を見つける
- 主体的かつ自主的な姿勢や発想力
- 友達の意見に耳を傾ける
- 意見に共感し譲り合う気持ち
- 意見を調整する力
このような経験を繰り返す中で社会性を育み、生涯にわたる人間関係の基礎となる土台を築いていきます。
思考力の発達
この時期の子どもは自分への自信を付け、色々なことに興味を示すようになります。
その中で、環境に関わり社会事象や自然事象に対する認識を高めたり、言葉や文字の世界にのめりこんでいきます。
例えば、
- ひらがなを読むことができる
- 自分の名前をひらがなや漢字を使って書くことができる
- 短いお話を作って披露するようになる
- 乗り物や動物、野菜、果物などの名前や用途を理解する
- 比較(長い短い・大きい小さい)が理解できる
- 平面から立体を想像できるようになる(つみきの隠れて見えない部分も理解する)
- 水に浮かぶもの、風向き、光と影の関係を理解する
などの認識が高まり、思考力が育っていきます。
自立への一歩
今まで培ってきた経験を活かして、自立への一歩を踏み出そうとしている6歳児。
この頃から、自分への思考が進み自分以外の大人や友達の存在や、特徴に気付いて自意識が芽生えていきます。
また、大人の言動や行動にも批判や意見を述べるようになる子も多く、大人っぽく成長して周囲を驚かせたり、自分自身も大人っぽく振舞おうとする姿が見られる。
例えば、
- 〇〇ちゃんと同じ可愛い髪型がいい!
- 僕も〇〇君のように速く走りたい!
- お世話をしてあげたい
などの他人と比較した意見を伝えてきたり、年長児を意識した言葉が出てくるようになったり、
- お父さん、帰ったら手を洗ってね
- お母さんさっきも同じこと言ってたよ
など、「はっ!」とさせられる意見が飛び交う事もありますが、まだまだ周囲の大人に甘えるような姿を見せることもあります。
このような経験を繰り返す中で自立心が芽生え、6歳児は進学への期待や不安に胸を膨らませていくのです。
6歳児への保育士の上手な関わり方は?
この時期の子ども達は、保育園の最年長児としての自信と誇りを持ち、就学に期待を膨らませながら、色々な事にチャレンジして自立心育んでいきます。
運動面では、身体的な成熟に合わせて、
- 跳び箱(4~6段)
- 竹馬(バランス感覚を鍛える)
- マット運動(前転・後転)
などの複雑な動きや、
- 鬼ごっこ
- 障害物リレー(毎回障害物の内容を変化させる)
- ミニサッカーゲーム(簡単なルールを子ども達と一緒に考える)
などの集団遊びを取り入れ、協同しながら遊ぶ喜びを伝えていきましょう。
また、絵本や紙芝居などの視覚教材を保育に取り入れる事によって、見たり聞いたりする機会を増やし想像力を豊かに育み、言葉や数的概念、文字を書く意欲に繋げられるように配慮することも大切です。
他にも、自分のイメージを自由に表現できる画材や用具を保育室に揃えておき、いつでも製作活動ができる環境を整備しておくのも良いでしょう。
この時期、異年齢の子ども達との交流や園外活動などを通して、自主と協調の姿勢や態度を学んで社会性を育んでいくので、できるだけ多くの人達と関わりが持てる機会を提供していくのも保育園としての役目になります。
最後に、いつでも一生懸命な子ども達ですが、時には集団生活に疲れ一休みしたいと思う時も多い事でしょう。
そんな時は、優しく話を聞いたり一緒に休息を取るなど、気持ちに寄り添いながら、保育士が心の拠り所になれるよう配慮していくことが大切です。