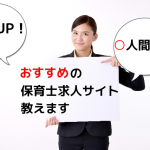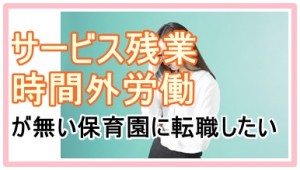スポンサーリンク
5歳児に見られる主な特徴とは?
- 運動能力の高まりにより、大人の動きと変わりなく活動できる
- 基本的生活習慣の定着
- 数をかぞえられるようになる(10~50程度)
- 集団行動ができる
- 友達同士で助け合い問題を解決することができる
- 自分の感情をコントロールすることができる
- 箸が上手に使えるようになる
- 思いやりの心が育つ
5歳児の心と体の発達を確認しよう!
運動機能の向上
ますます運動能力が伸びる5歳児ですが、
- 大人と同じスピードでの歩行
- 平均台
- 竹馬
- ブランコの立ちこぎ
などの動きを習得し、バランス感覚が備わっていくと同時に、
- ドッジボール
- 縄跳び
- 鬼ごっこ
- かくれんぼ
などの全身を使った複雑で簡単なルールがある遊びを好むようになり、幅広い動きに対応できるようになります。
また手先も器用になり、
- ハサミを使い紙を曲線に切る
- ホチキスやのり、カラーペンなど用途に合わせて使い分けることができる
- 雑巾絞りができる
- 紐を結ぶ動作が上手くなる
など、自分でできる細やかな動きが増える事で、自主性や自立性を日々育んでいきます。
基本的生活習慣の向上
5歳児になると、生活する上で重要なほとんどの動作を自分でこなせるようになり、大人の指示がなくても見通しをもって行動できるようになります。
例えば、
- 朝起きたら顔を洗う
- 食事の前に手を洗う
- お風呂から上がったらパジャマを着る
などの日常動作を率先して行うようになったり、
- おもちゃや絵本を大切にする
- 自ら片付けをする
など、生活スペースを整え過ごしやすい環境を作る大切さを理解し生活できるようになります。
また、道徳観念の理解が進み、決められたマナーが守れるようになり、公共の場でも落ち着いて行動できるようになりますし、人の役に立つことを誇らしく思い下の子の面倒を見たり、大人の手伝いを積極的にするようになります。
こうした経験を積み重ねることで、相手を気遣う優しい心を育て自ら感受性を高めていきます。
集団としての関わり
4歳児の頃と比べ、5歳を過ぎると物事の違いや特性を理解し比較するようになります。
例えば、
「お父さんはヒゲが生えて背が高いけど、お母さんはヒゲがないし背が低い」
「犬はワンワンと吠えて耳が短いけど、ウサギは耳が長くて吠えない」
など、2つ以上の特徴や特性を答えられるようになります。
また、時間や空間の認識も進み、時計の時間を把握し、時系列に文章を組み立てることができたり、積み木やブロックなどの立体的なおもちゃを上手に扱えるようになります。
5歳児は、目的を持った集団行動も盛んになり、今まで以上に仲間を大切にする気持ちが育っていきますし、楽しく活動するために各々の役割を決めたり、遊びのルールを守ったりと仲良く遊ぶための方法を考えるようになります。
ですがその一方で、自分の主張や相手の意見をお互いにぶつけ合うことも多くなり、ケンカや言い争いが起こることも増えますが、すぐに大人に頼るのではなく、友達同士で問題を解決しようという姿勢が見られるようになります。
このようなやり取りを繰り返す中で、集団としての団結心が高まり友達との絆が強くなっていきます。
思考力の始まりと言葉
この時期の子どもは、今まで培ってきた経験を土台に、自分で考え判断するという社会生活において欠かせないスキルを身に付けていきます。
しかし、おかしいと思った事柄に対しては反発心をを見せながらも、ネガティブな気持ちをポジティブに言い換える言語調節を行うことで気持ちを整理できるようになります。
また、他人を「それはおかしい」「〇〇君(ちゃん)だけずるい」などと批判したり、逆に批判されることも増えますが、次第に自分の気持ちを相手にわかりやすく伝える方法や、指摘を素直に受け入れる力を身に付けることで、相手を許し認めることを学び、思考力の礎を築いていきます。
5歳児くらいになると1~50程度の数を数えられるようになり、名前・年齢はもちろんのこと、自分の意見を文章にして伝える力がついていくと同時に、
「じろじろ見ないで!」
「かみなりがドカンと落ちた」
など、擬態語や擬声語を上手に使えるようになります。
会話は大人とほとんど変わりなく、楽しいおしゃべりをたくさん展開してくれます。
友達との関係
集団活動が多くなり、仲間と過ごす時間の中で自分の感情をコントロールする術を身に付けて成長していきます。
このような成長が、集団の結束力を高め、個々の成長を促していくことに繋がっていきます。
また、集団生活を通して子ども達は思いやりの心を育み、仲間の中の一人と言う自覚を持って行動するようになります。
そして、友達への信頼や親しみを感じるようになります。
5歳児に保育士はどのように関わればいいのか?
保育園では最年長クラスのお兄さんお姉さんとして生活している5歳児。
この時期の子どもは、自分の意思や判断で行動できるようになり、積極的に人と関わったり物事に取り組む姿が見られるようになります。
そんな子ども達の主体性を高めるためには、
- 保育園内の縦割り活動
- 地域交流
など、色々な人と接する機会をどんどん増やしてあげるのも保育士としての役目です。
また、生活の中で取り組んでいる課題やお手伝いなど、どんなに小さなことでもしっかり褒めてあげることが大切です。
なぜなら、自分でできることが増える事で、「頑張ったね」「よくできたね」と大人に声をかけられる回数も減り、自己肯定感や自身が揺らぎやすい時期でもあるからです。
保育士にできることは、
- 園児一人一人の行動に目を配る
- 一日一回は良い所を褒める
- どんな些細な出来事でも気付けるアンテナを常に張り巡らしておく
ことがとても大切になります。
この時期、ひらがなが書けたり、数字を100まで数えられる子も中にはいますが、まだまだ関心が無くて覚えていない子もいるでしょう。
そんな時、保育士が執拗に教えてしまうとストレスを感じたり、数字や文字が嫌いになってしまう子までいるので、日常生活の中で徐々に関心が持てるように、歌や遊びを通して伝えていくようにしましょう。
小学校に入るくらいまでは、数字や字を覚えるより、基礎となる体作りの方がよっぽど大切です。
運動面では、集団で取り組む遊びを取り入れ、活発に体を動かせる環境を提供し、運動機能を高める内容の保育を考えましょう。
例えば、
- 鬼ごっこ
- 氷鬼
などのルールがある遊びや、
- 縄跳び
- ドッジボール
など複雑で俊敏な動きが求められる遊びなどが好ましいといえます。
最後に、子ども達は保育士や大人の行動を常に観察しながら過ごしています。
お手本となる保育士が、ルールを破ったり約束を守らないのでは説得力がありません。
子ども達の模範になれるよう、交通ルールを守ったり、正しい立居振る舞いで行動するように心がけましょう。