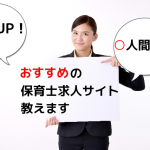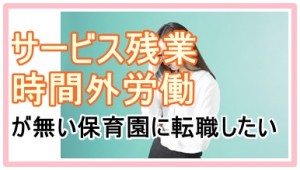スポンサーリンク
4歳児(年中)の主な身体や言語の特徴
- 運動能力の発達に伴い、全身のバランスがとれる
- 我慢ができるようになる
- イメージを膨らませて想像の世界で遊ぶことができる
- 葛藤を経験する
- 自然物に興味を持ち積極的に関わる
- 嘘をつくようになる
- 色々な気持ちが理解できるようになる
4歳児の発達傾向と特徴
運動能力の発達
3歳児に比べると、4歳児はしっかりとした足取りで歩いたり、走ったりができるようになり、運動量もますます増えていきます。
バランス能力の発達に伴い、思いのままに体を動かすことができるようになるので
- 片足とび
- スキップ
- リズムに合わせたダンス
などの全身を使った動きから、遊具や道具を使った遊びに挑戦するなど、意欲的に活動する姿が見られます。
この時期の子どもは、運動機能だけでなく手先も器用になり、
- ハサミが上手に使えるようになる
- 小さいビーズに紐を通す
- 少し難しい折り紙に挑戦する
など、遊びのバリエーションが増えていきます。
また、遊びの途中で大人を呼んだり話しかけるなど、2つの行動を同時に行えるようになるので、より一層遊びの時間を楽しく過ごせるようになります。
身近な環境への興味や関心
4歳にもなると、今まで自然物(水・砂・草花・虫・鳥・空・木)に興味を示さなかった子も興味を持ち始め、自分の感覚を総動員しながら遊びを体得していきます。
例えば、
- 草花を摘んで冠を作る
- 虫を捕まえて観察する
- 砂でお城を作る
- 鳥の鳴き声や夜空の星に関心を示す
など、より豊かな感覚を得ると同時に、認識力や色彩感覚も育んでいきます。
自然物と触れ合う経験から、子どもは想像力豊かな世界を築き上げ、喜びや幸せを感じるようになります。
想像力の広がりと葛藤
行動範囲が更に広くなったことにより、想像力が更に広がり、現実と空想の世界を行き来し、イメージを膨らませながら遊びを展開していきます。
例えば、
「ぬいぐるみが〇〇って言ってるよ」
「太陽が笑ってた」
など比喩的な表現を使う事も増えてきます。
大人が聞くと、一見嘘をついているように聞こえてしまう保育士もいるかもしれませんが、空想の中で現実と取り違えて話をしている場合が多いので心配しないでください。
こうした想像の世界の面白さや、へんてこさを楽しみつつ、同じ年中さんやそれ以外の友達とイメージを共有しながらごっこ遊びを楽しみます。
また、4歳頃から自我の成長により、自分以外の人に目を向けじっくり観察するようになり、逆に自分も見られていることに気付き、自意識をもって行動するようになります。
そして、自分の意思を貫きたいという思いと、それができない辛さや不安という葛藤を周りの大人に共感してもらったり励まされたりしながら、我慢や人の気持ちを理解することを覚えていきます。
また、想像力の発達により、一人取り残されることへの不安や恐怖を敏感に感じ取り、
- お化け
- 暗闇
- 大きな音
などが苦手になる子もいます。
友達との関わり
友達と関わることに対して喜びや楽しさを感じ、どんどん繋がりが深まっていくのが4歳児です。
この時期、お互いに負けたくないという競争心が生まれ、主張をぶつけ合いながらケンカに発展してしまう事も多々あります。
しかし、このような意見のぶつけ合いを経て、相手の主張を受け入れたり、逆に受け入れてもらう経験を積み重ね、人が生きていく上で大切な社会性を身に付けていきます。
また、友達同士で譲り合ったり助け合うなどの協調性を持ちつつも、
「これがほしい!」
「おもちゃを貸したくない」
などの自己を発揮し、その過程を繰り返す事で、自分達だけで問題を解決する力を身に付け、自己肯定感や他人を受容する感情を養っていきます。
言葉(日常会話)の発達
日常会話がスムーズに進むようになり、
- 現在
- 過去
- 未来
の言葉を、使い分けることが無理なくできるようになります。例えば、
「昨日〇〇ちゃんと砂場で泥団子作った」
「明日はお楽しみ会でダンスをするよ」
など、自分の経験したことや思ったことを上手に伝えられるようになるのも年中さんの特徴です。
また、保育士1人1人の名前や誕生日、年齢、家族の名前などを記憶して教えてくれるようになり、会話が弾んで楽しくなるでしょう。
しかし、時には先生や友達の気を引くために暴力的な言葉を使ったり、人を悲しませる嘘をつくこともあるので注意しておきましょう。
4歳児に保育士ができること、やるべきこと、関わり方
3歳児と比べると格段に表現力が高くなり、自分の思いや経験したことを保育士に伝えてくる機会も増えてくるので、コミュニケーションを取る時間をゆっくり取れるように時間の使い方を少し工夫してみましょう。
☑ 子どもとの会話、関わり方
もし、「先生今忙しいから」と話を中断したり、「後で聞くね!」と約束したのに聞かなかった場合、子どもたちは「自分が受け入れられていない」と感じ、心を閉ざしてしまう原因にもなりかねないので注意が必要です。
また、現実と想像の世界を重ねてしまう時期なので、素っ頓狂(すっとんきょう)なことを口にする時もありますが、怒ったり面倒くさがったりせず、一緒に楽しむくらいの気持ちをもって関わることが大切です。
☑ ケガに注意する
運動面では、ブランコやジャングルジム、滑り台などの固定遊具から、走る、跳ぶなどの活発な動きまでオールマイティーにこなせるようになるので、必然的にケガの危険性も高まってしまいます。
保育士は、遊びや運動を促しながらも、しっかりと子どもの動きに目を配り、未然にケガを防ぐ努力を怠らないよう心掛けましょう。
☑ 手先と脳の発達を促す
また、手先の発達を促すために、クレヨンやマーカーだけでなく、絵具や色鉛筆、粘土なさまざまな材料を用意し、表現することの楽しさや好奇心を掻き立てる工夫をするといいでしょう。
☑ 子どもの世界に大人が無理に入らない
最後に、この時期の子どもは、自己主張と協調の狭間で悩んだり葛藤しながら徐々に社会性を身に付けていきます。
その中で、お互いの主張がぶつかり合うケンカも激しくなり、保育士の仲裁が必要になる機会も増えていきます。
この時、すぐに保育士が仲立ちして解決するのではなく、危険が無い程度に見守り、お互いが助けを求めてきたときに初めて仲裁に入り、「ケンカの理由」や「どうしたら解決できるのか?」について子どもたち自身に考えさせるようなサポートを心がけましょう。
また、正直に話せたりお互いに謝ることができたら、しっかり褒めてあげましょう。