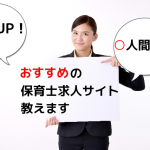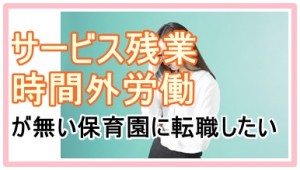スポンサーリンク
3歳児の主な特徴
- 運動機能が著しく伸びる
- 基本的生活習慣の自立(食事・着脱・排泄)
- 言葉の習得により、知的好奇心が高まる
- 平行遊びが多い
- 遊びを通して社会性が発達する
- 予測や目的をもって行動できる
3歳児の発達の流れと特徴
3歳児の運動機能の成長
この時期の子どもは脳神経の成熟により、体のバランスや動きをコントロールする能力が育ち
- 歩く
- 跳ぶ
- 走る
- 投げる
- ぶら下がる
- 蹴る
などの基本的動作から、
- 短時間の片足立ち
- 足を交互に出して階段を上る
- 後ろ歩きをする
などの複雑な動作まで、幅広い運動能力を身に着けていきます。
基本的な生活習慣の自立
また、運動機能の発達に比例して
- 食事
- 着脱
- 排泄
などの基本的生活習慣の自立が進んでいきます。
- 手先が器用になる
- 食事をこぼさずに食べることができるようになる
- ハサミを上手に使えるようになる
- 一人で靴や衣類の着脱ができるようになる
- 排泄のタイミングがつかめるようになる
など、子どもの中で「自分でやりたい!」という自立心が芽生え、徐々に大人の手助けを拒むようになります。
3歳児の言葉の発達と成長
3歳児は最も言葉を吸収する時期なので、理解できる言葉が急激に増加し、大人や友達を交えた会話のやり取りが一気に盛んになります。
話し言葉も長くなり、「イチゴ食べたい」という表現が、「ご飯食べてからイチゴ食べていい?」など助詞を使った文章を使えるようになります。
また、話すことの楽しさを知り
「こんにちは」
「おはよう」
「さようなら」
などの挨拶を積極的に行い、自分からコミュニケーションを取ろうとする姿も見られます。
知的好奇心のが高まり、
「なんで?」
「どうして?」
などの質問が多くなり、大人を困らせることもしばしばですが、根気よく付き合い興味や関心に応えることで、より多くの言葉や表現を身に着けて成長していきます。
遊びの変化と社会性の発達
2歳頃のイヤイヤ期も落ち着き、コミュニケーション能力の発達により、友達と一緒に遊ぶ姿も見られますが、まだまだ同じ場所で同じ遊びをしながらそれぞれ単独で遊ぶ”平行遊び”を好みます。
しかし、時折他の子の遊びを真似たり、おもちゃの貸し借りを行うなど、相手の存在を意識しながら遊ぶ姿も見られるようになります。
また、少しずつ遊びのルールが理解できるようになり、頻繁に起こっていたおもちゃの取り合いやかんしゃくが減り、同じイメージを持って遊びを楽しむことができるようになります。
そして、友達と遊んだ経験や、大人の行動、日常の出来事をよく観察し、遊びの中で再現しながらごっこ遊びを発展させていきます。
例えば、動物になりきって遊んでみたり、お母さんの真似をしながら料理を作ったりと、想像力を膨らませながら遊ぶことができるようになります。
このような遊びを繰り返す中で周囲への関心や観察力が生まれ、徐々に自我が成長していき、「ぼく」「わたし」と自分のことを認識すると同時に、友達や家族、他人との区別をつけながら社会性を育んでいきます。
3歳児への保育士の援助のポイント
3歳児は、知的好奇心の高まりと共に、周囲の大人や友達とのやり取りが増え、色々な経験を積みながら社会性を身に付けていく大切な時期だといえます。
そんな子どもの興味や好奇心は、「なんで?」「どうして?」などの質問となって現れ、時には保育士に対して簡単には答えられないような子どもながらの疑問を投げかけてくることもあるでしょう。
そんな時は
「なんでかな?」
「○○君(ちゃん)はどう思う?」
と逆に聞き返して思考力を養ったり、「先生と一緒に考えようか?」など、子どもの好奇心を更なる関心や興味へと導いてあげてください。
また、自我の発達に伴い、「私は〇〇したい!」という気持ちが高まり、大人が手伝う事を拒否したり、他者とぶつかりあうことも多くなり、保育計画通りに進まないこともあるでしょう。
そんな時、保育士も人間なのでイライラしたり焦ってしまうこともあると思いますが、子どもの主体性を大切にして時間の許す限り見守り、集団行動を優先させる場合は、感情的にならずに言い聞かせて対処するように心がけましょう。
また、子ども同士のケンカが起こった際、危険が無い場合はすぐに仲立ちせずに、相手の思いに気付き折り合が付けられるように見守り、必要な場面でお互いの話しを聞いて解決へと導いてあげましょう。
このような保育士の関わりが、好奇心を刺激したり、他者への理解を深めることに繋がり、社会性を育んでいきます。